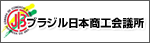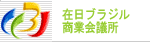会報『ブラジル特報』 2005年5月号掲載 堀坂浩太郎 (上智大学 教授)
|
|
国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指している日本、ブラジル、ドイツ、インド4カ国による共同行動がしばしば新聞紙上で取り上げられるようになった。昨今の情勢を考えると安保理改革の決定にはなお時間を要することになりそうだが、長年、日伯関係の動きを観てきた者としては、ブラジルとの間でようやくワールドワイドの協力関係が出来つつあるように思えて感慨すら覚える。 それというのも、日本とブラジルは移住以来長い年月の二国間関係がある。近年においても一般の目には貿易や投資、経済協力といったバイラテラルな側面が目立ち、外交畑の人を別にすれば、国際場裏での両国の交流・協力についてほとんど知り得る機会がなかったからだ。 いうまでもなく、同国との間には、短期の国交断絶の歴史はあったものの、アジアの隣国と比べると、わが国の対外関係において「負の遺産」である第二次世界大戦の影響はほとんどない。むしろ日系人の存在や戦後いち早く着手されたウジミナスやセラードといった共同事業の記憶もあって、「仲の良いのは当たり前」といったイメージが、われわれ日本人のえてして陥るブラジル観ではないであろうか。 しかし親戚付き合い的な意識は、相手の現状や変化をきちんと見ていない恐れもある。そればかりか、「せっかく訪ねてきてくれたのに」どう思われるかばかりが気になり、お土産探しに奔走することにもなりかねない。まして多額な持参金を持ったライバルが登場するとなると、相手とそちらの関係ばかりが気になり、本来、訪問の第一義的な目的である真剣で突っ込んだ対話がますますお留守になりかねないのである。こうした態度では、お互い十分好意は持っているのに、親愛のすれ違いといった事態を招くおそれすらある。 現状を考えると、日本のブラジル認識には、こうした危うさを感じさせる側面があるように私には感じられる。両国間の過去の友好関係は資産として大事にしながら、今日的な問題、とりわけ世界のなかで果たさなければならない日本とブラジルのそれぞれの役割と責務について、じっくりと意見を交換し詰めていくことが必要な時に来ているのではないであろうか。世界を視野に入れた話し合いは、安保理だけに終らせてはならないと思う。 ブラジルの外交は、カルドーゾ政権からルーラ政権にかけて極めて能動的になった。実際に、世界貿易機関(WTO)における関税一括引き下げ交渉、いわゆるドーハ開発ラウンドにおける交渉ひとつをとってみても、ブラジルの存在はもはや単なる一途上国ではなくなっている。2003年9月のカンクン閣僚会議での途上国グループG20の結成や、米国、EU(欧州連合)、オーストラリア、インドとともにNG5として農業交渉の道筋をつけた昨年7月の枠組み合意を引き合いに出すまでもなく、通商交渉の重要な一角をなしている。 歴史的にみると、これまでにも「進歩のための同盟」の母体となったクビシェッキ大統領による「パンアメリカン作戦」の提唱(1950年代後半)や、クワドロス大統領による「第三世界外交」(60年代前半)、あるいは軍事政権による「全方位外交」(70年代)など特徴的な外交もみられたが、どちらかといえば「ロー・プロフィアル」、すなわち目立たないことを良しとしてきたところがあるのがブラジル外交であった。 「資源国」「新興工業国」「中進国」としてのポジションを最大限活かすためのプラグマティック(実利主義的)な選択として、こうした姿勢がとられてきたといえよう。 しかしここ数年、ブラジルの外交は明示的になっている。とりわけルーラ大統領は、「空飛ぶ大統領」との批判が国内から出るほどで、2003年1月の就任以来外遊を重ねている。訪日も一連の外遊の一環といってしまえばそれまでだが、むしろワールドワイドに展開し始めた同国の対外関係形成戦略を知る絶好の機会として受け止めたい。 筆者のみるところでは、その戦略はおよそつぎの4つのフロントラインに集約できそうだ。すなわち、①国連やWTOなどの多国間交渉、②伝統的な貿易相手国、特に米国およびEU(欧州連合)との通商交渉、③メルコスール(南米南部共同市場)を足場とする地域外交、④アジア、アフリカ、中近東の域外途上国、中でも中国、インド、韓国、南アフリカ、エジプトなどの地域有力国との関係強化、である。 しかも、これらのフロントラインを巧みに絡ませてブラジルの国際的なポジション確立に動いているとみてよいであろう。ルーラ大統領は本稿執筆のこの時期にも、ナイジェリア、ガーナなどアフリカ5カ国を歴訪中だし、訪日前の5月上旬にはブラジリアで南米・アラブ首脳会合を予定している。前者は就任以来4度目のアフリカ訪問となり、後者は2003年12月のアラブ5カ国歴訪の際に約束していたものである。 米国が主導するFTAA(米州自由貿易圏)結成交渉では、対米抵抗勢力としてブラジルが報じられることが多いが、それは単純すぎる見方かも知れない。米国のお膝元であるカリブ海地域の安定ではハイチに派遣された国連平和維持軍の中核を成している。EUとメルコスール間での連合協定の交渉を進めながら、それをFTAA交渉のカードにしようとの言動も垣間見られるのである。 日本は上記の4つに分けてみたブラジルのフロントラインのいずれとも利害を有するわけで、多面的外交を繰り広げている同国がどのような世界観や戦略を持とうとしているのかに注目し、大統領の訪日の機会をとらえて、政府はもとより経済界もその考え方を引き出し理解しておく必要があろう。そうした努力と成果は、バイラテラルな案件を長期的に支えてくれる信頼のベースともなりえる。 直近の事項でも、急騰する一次産品価格の先行きを考えれば、大豆を中心とした食糧や鉄鉱石・非鉄金属の供給余力をもち、石油自給化の目処をつけたブラジルとは、世界を視野に入れて供給と価格の安定を話し合っておくべきである。エタノールの供給についても、そうしたコンテキストの中に含めて議論されてもよいのではないであろうか。 セラードにおける農業協力が、日本への直接的な供給ではなく、世界全体を視野に入れた食糧増産を意図して始められたことを忘れてはならない。 ブラジルと日本はそれぞれ国連環境開発サミット(リオデジャネイロ、1992年)と京都議定書が採択された地球温暖化防止京都会議(1997年)を主催している。環境問題に取り組むメッセージが二カ国共同で発せられてもよいであろう。今年秋の国連総会で、貧困撲滅のためのミレニアム開発目標の再点検があることを踏まえれば、ルーラ政権が進める「飢餓撲滅プログラム」(Programa 2008年には移住100周年を迎える。日伯関係は、かつては日本からブラジルへ、そして現在ではブラジルから日本へと大量の人の移動を有する、わが国の対外関係においては稀有なケースでもある。親戚付き合い的な意識を持ちかねない理由もこうした点にあるのだが、両国の若い世代のことを考えれば、二国間のことだけでなく、ワールドワイドの問題においても広く意見交換ができる素地を両国間に形成しておく必要がある。そうすることによって、将来へのより積極的な展望を提供することになろう。 昨年9月の小泉首相の訪伯から1年も立たないうちに実現したルーラ大統領の訪日には、大所高所からの議論を期待するとともに、古くて新しい課題だが、互いに相手のことをよりよく知るためのインフラづくりの機会となることを祈念したい。 |
日本ブラジル中央協会|魅力に溢れたブラジルへの道しるべ|ブラジルの経済・イベント情報~ポルトガル語講座開講中です!
MENU
関連情報
- HOME »
- 関連情報 »
- ブラジル特報 バックナンバー »
- 2005 »
- 世界を視野に入れた交流を


 2025年5月号
2025年5月号