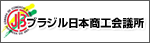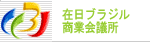| 会報『ブラジル特報』 2011年1月号掲載 文化評論 岸和田 仁(協会理事)
|
|
ブラジルの歴史や社会について理解を深めるための必読書といえば、たちまち何冊か思い浮かぶが、前山隆『移民の日本回帰運動』(NHKブックス、1983年)は間違いなくその一冊であろう。終戦直後のブラジル日系社会における「勝ち組、負け組」抗争を歴史人類学の視点から解読した快著であるが、「勝ち組」現象は第一次大戦直後、米国で展開されたジャマイカ出身のマーカス・ガーヴェイによる「アフリカ回帰運動」と共通点の多い千年王国運動といえる、との解釈は実に刺激的であった。「アフリカをアフリカ人の手に」のスローガンを掲げ、「新大陸の黒人は白人社会に留まっている限り平等な地位をえることはない、アフリカに戻って黒人独立国家を建設することが真の黒人解放の道である」、と主張したブラック・ナショナリズムの先駆的運動と、多くの共通点を持つ「勝ち組」は千年王国論として成立したのだ、という指摘は、今でも新鮮である。 また、『異文化接触とアイデンティティ』(御茶の水書房、2001年)に収録されている、1975年に発表したコロニア文学論も今や”伝説的な”論文だ。コロニア文学のあり方は《加害者不明の被害者》の文学であり、抵抗の文学でも告発の文学でもなかった、「目前の日常的事象を世俗的日常性のままで把えた”籠の鳥”文学であり」、かつ「コロニア的現実を存在しないとわめいて小児病的抽象を行う脱色文学」だ、という強烈な批評であったからだ。 さらには、『民族交錯のアメリカ大陸』(山川出版社、1984年)の一章として書かれた「ブラジル社会−人種と文化のるつぼ?」も、人種デモクラシー論への批判論文として必読だと思う。「ブラジル社会の多様性には多くの次元がある」として、社会学者フロレスタン・フェルナンデスの「ブラジルには、人種偏見がない、という偏見がある」という指摘を敷衍しながら、「ブラジルは多元的社会ではないし、社会観、国家観、イデオロギーとしても多元主義の伝統はきわめて薄弱である」と主張し、「現代ブラジルにおいては、さまざまな人種的な範疇とアイデンティティが、エスニックな範疇やアイデンティティとならんで復活し、新生しつつある」と結論付けている。 このように実にラディカル(根源的)な既製アカデミズム批判を展開してきた文化人類学者の日系社会研究としては、『非相続者の精神史』(1981年)、『エスニシティとブラジル日系人』(1996年)、『ドナ・マルガリーダ渡辺−移民・老人福祉の53年』(1996年)、『風狂の記者−ブラジルの新聞人三浦サクの生涯』(2002年)(出版社はいずれも、御茶の水書房)などの文学性の高い著作群があることは、周知のとおりである。 この前山教授の自伝的回想録『文学の心で人類学を生きる』(御茶の水書房)がこのほど発刊されたとなれば、読みさしの文庫本をうっちゃってでも、熟読せざるを得ない。すさまじい研究人生への熱い思いが書かれた文章からも行間からも湧き出てくる作品であり、タイトルが著者の心性を象徴しているように、詳細極まりないノンフィクション回想記録であるからだ。 1933年札幌で生まれ、岩手で中学・高校時代を過ごし、若き代用教員として生活費・学費を調達した極貧の苦学生が、「駅弁大学」で哲学を学び、レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』に感動してブラジル渡航を決断する。独学でポルトガル語を学び、サンパウロ大学の給費留学生として勉学とフィールド体験を始める。テキサス大学、コーネル大学、サンパウロ大学の共同研究プロジェクト「現代複合社会における文化変容」の調査員として参加したことで、学問的実績もさることながら、多様な人脈を広げることになり、この人的ネットワークが多義的に機能してブラジル社会研究が一層進む。並行して雑誌「コロニア文学」を舞台とする日系文学運動にも能動的にコミットしていく。 優等生として過ごした米国留学を回想する部分は少々退屈であるが、サンパウロ人文科学研究所での活躍、香山六郎自伝を編纂した苦労など、日系社会研究の”舞台裏”がみえてくるのは実に興味深いものがある。生活費捻出のため、駐在商社マン子弟の家庭教師もしたが、そのなかに後の某有名学者(「小泉チルドレン」の一人)もいた、といったエピソードも面白かった。ともあれ、著者の負けず嫌いの向学心とあらゆる社会現象に対する過剰なほどの知的好奇心に読者は圧倒されることになろう。 |
日本ブラジル中央協会|魅力に溢れたブラジルへの道しるべ|ブラジルの経済・イベント情報~ポルトガル語講座開講中です!
MENU
関連情報
- HOME »
- 関連情報 »
- ブラジル特報 バックナンバー »
- 2011 »
- 前山 隆の『文学の心で人類学を生きる』を読む


 2025年5月号
2025年5月号