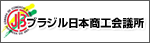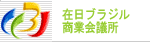| 会報『ブラジル特報』 2010年3月号掲載
岸和田 仁(協会理事)
|
|
「フェジョワダというブラジル料理を食べた。これは牛や豚の内臓と黒豆をいっしょに煮込んだもので、日本の鍋焼きウドンのようにもってくる。中から何が出てくるかわからぬといった感じで、少々気味が悪い」と書き記したのは、毒舌で知られた評論家大宅壮一だ。彼が1954年ブラジルを訪問した時の文章で、ブラジル人の唾液を限りなく刺激するフェイジョアーダを鍋焼きウドンと比較するとは、その直截的な表現は今日の読者にも面白い。 今回は、ここ10年くらいの間に発表された社会学者や歴史学者による関連論文を参照したうえで、このブラジル国民料理の歴史を急ぎ足で追いかけてみたい。 まず、フェイジョアーダという単語が文献に登場したのはいつか。代表的な国語辞典とみなされているHouaiss辞典によれば、それは1813年である。ブラジルを旅行した英国人ウォーシュが、「リオ住民の主食といえるのは、フェイジョン(インゲン豆)と塩漬豚脂+塩干牛肉のミックスだ、人によっては塩干肉やファリーニャ(マンジオッカ粉)、オレンジを付加する」と記録しているのは1808年のことだ。1817年ミナスを旅したフランスの博物学者サンティエールは、「黒インゲン豆は金持ちのテーブルでは欠くことの出来ぬ献立となっており、これは貧乏人の食事についてもほとんど同じである」と記録しているし、ドイツの博物学者マルティウスは、1818年ミナスを旅しながら「ここの主食は、黒インゲン豆+フバ(トウモロコシ粉)+塩漬豚脂のミックスであり、バイーアではインゲン豆が基礎的な主食で、黒人奴隷についても同様だ」と書き記している。 レストランのメニューとして初めて新聞紙面に登場したのが、「ディアリオ・デ・ペルナンブーコ」紙1833年8月7日で、「テアトレ・ホテル」では木曜日に“ブラジル風フェイジョアーダ”が供される、という記事だ。リオの新聞では、1849年1月5日付け「ジョルナル・ド・コメルシオ」紙の広告欄に「美味しい、“ブラジル風フェイジョアーダ”」が初めて登場し、「毎週火曜日と木曜日に、美味しいフェイジョアーダを供しています(後略)」とある。すなわち、料理として確立するのは19世紀中ごろ、といえるだろう。 通説によれば、この料理は、「主人が食べなかった豚肉の部位(鼻、尻尾、耳、内臓など)とフェイジョン豆を鍋で煮込んだ、もともと黒人奴隷の低級な料理だったが、支配層も食べたらおいしかったので、階層の上下を問わず国民全体が食べるようになり、伝統的料理となった」のであるが、このセンザーラ(奴隷小屋)から生まれた料理という“常識”が作られた神話でしかなかったとして否定され、南欧起源説が研究者ばかりか一般メディアでも受け入れられるようになったのは1990年代に入ってからである。 白インゲン豆に腸詰、モルシーリャ(豚の血腸詰)、塩漬け豚脂、豚足、豚の耳などを煮込んだ、スペイン北部料理ファバーダも、インゲン豆と肉類のシチューである南フランス料理のカスレも、いずれの料理においても、豚の耳や尻尾、内臓は“二級ないし三級品”として足蹴にされるようなことは全くなく、貴重な食材として大事に扱われてきた では、南欧から移入された料理が、何故、ブタのお余りの部位を活用して黒人奴隷が作り上げた料理だ、との通説を生み出してしまったのか。筆者の推論は、奴隷料理神話が意図的に創作された、ということではなく、大農園の料理を担当していた黒人奴隷女性たちが自ら工夫してフェイジョアーダのレベルを上げていき、その事実から自然と「黒人女性が創り上げた料理なのだから、フェイジョアーダはセンザーラから生まれたのだ」という民衆理解が一般化したのではないか、というものだ。ともあれ、フェイジョアーダは南欧(本来の起源)+先住インディオ(ファリーニャ)+アフリカ(味付け)という複数の食文化の三位一体的混合の進化結果である以上、ブラジル的な意味において”正統派料理”と断言してよいだろうし、こうした議論を頭でなく胃袋で楽しむのが、正しいブラジル文化研究だろう、と思うが、さて。 |
日本ブラジル中央協会|魅力に溢れたブラジルへの道しるべ|ブラジルの経済・イベント情報~ポルトガル語講座開講中です!
MENU
関連情報
- HOME »
- 関連情報 »
- ブラジル特報 バックナンバー »
- 2010 »
- 国民食フェイジョアーダの歴史を散歩する


 2024年3月号
2024年3月号